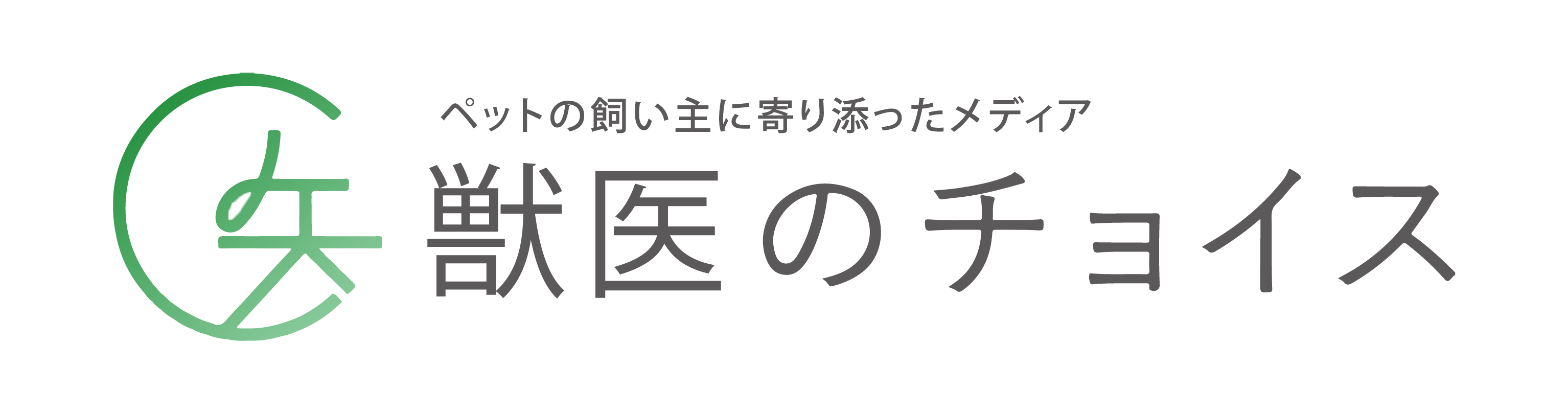目次
愛猫が病気と診断されたとき、「どの療法食を選べばいいの?」「本当に食べてくれるのかな?」と戸惑う方は多いはずです。療法食は、ただの特別なごはんではなく、病気の進行を防ぎ、猫の健康寿命を支える大切なケアのひとつ。
とはいえ、種類も多く、味の好みや費用の問題、続け方など気になる点も尽きませんよね。この記事では、猫の代表的な病気に対応した療法食の種類や選び方、食べてくれない時の工夫、やめる判断の目安など、飼い主さんが本当に知りたい情報をわかりやすく解説していきます。
猫の療法食とは?一般食との違い

猫の療法食とは、特定の病気や体調不良を抱える猫に対して、栄養バランスや成分を調整して作られた特別な食事のことです。
たとえば、腎臓に負担をかけないようリンやたんぱく質を制限したフードや、尿路結石の予防を目的としたミネラル調整食などがあります。一般的なキャットフードは「健康な猫を対象」に設計されていますが、療法食は「治療や健康管理を目的」として使われる点が大きな違いです。
市販品のように自由に与えるのではなく、基本的には獣医師の指導のもと、猫の体調に合わせて慎重に選び、使う必要があります。
猫の療法食が必要になる代表的な病気と目的

療法食は病気ごとに目的が異なります。ここでは特に多い腎臓病や尿路疾患、アレルギー、肥満などに対応した療法食の特徴を解説します。
腎臓病の猫に適した療法食
腎臓に負担がかかると、老廃物を体外にうまく排出できなくなります。腎臓病用の療法食では、たんぱく質・リン・ナトリウムを抑え、体への毒素蓄積を減らすことが目的です。
また、カロリーを確保するために脂質はやや高めに設計されていることが多く、筋肉量を保ちながら腎機能を支える工夫がされています。症状の進行を抑え、QOL(生活の質)を維持するサポートになります。
尿路結石・下部尿路疾患向けの療法食
猫は尿路トラブルを起こしやすく、結石ができると排尿困難や血尿を引き起こすことがあります。療法食では、尿のpHバランスを調整し、ストルバイトやシュウ酸カルシウムなどの結石の形成を防ぐ働きがあります。
さらに水分摂取を促す設計がされており、尿量を増やして老廃物の排出を助けるのも大切なポイントです。予防と再発防止に役立ちます。
アレルギー・食物不耐症用の療法食
皮膚のかゆみや嘔吐、下痢が続く場合、食物アレルギーや不耐症の可能性があります。こうした症状に対応する療法食では、原因となりやすい牛肉・小麦・乳製品などのアレルゲンを除去し、加水分解たんぱく質や限定された原材料が使われています。
腸内環境のバランスを整える成分を含むものも多く、消化吸収を助けながら症状の緩和を目指します。
糖尿病や肥満に対応する療法食

猫の糖尿病や肥満は生活習慣と深く関わっており、食事療法が基本になります。糖尿病用のフードでは、血糖値の急激な上昇を防ぐために、炭水化物が制限されており、食物繊維を豊富に含むものが主流です。
肥満対策には、低カロリーながら満腹感を得やすい設計がなされ、ダイエットを無理なく続けることができます。体重管理が合併症予防につながります。
猫の療法食を選ぶときの5ステップ

猫に合った療法食を選ぶには、いくつかのステップを踏むことが大切です。ここでは、失敗しないための判断基準を5つのステップでご紹介します。
まずは必ず獣医師に相談する
療法食は薬と同じく「症状に合ったものを選ぶ」必要があります。ネットの口コミや見た目だけでは判断できないため、まずは獣医師に猫の健康状態をしっかり診てもらいましょう。
血液検査や尿検査の結果をもとに、必要な栄養調整の方向性が決まります。自己判断で与えてしまうと、かえって症状を悪化させてしまうケースもあるため注意が必要です。
病気・症状に合った目的別の療法食を確認
腎臓病・尿路結石・アレルギーなど、それぞれの病気に応じて栄養成分の調整ポイントは異なります。目的に合った療法食を正しく選ぶには、商品ラベルの記載や獣医師の説明をしっかり確認しましょう。
例えば「結石の溶解用」と「予防用」では役割が異なり、誤った選択をすると効果が得られない可能性もあります。
味・食いつきの相性をチェックする
いくら栄養バランスが整っていても、猫が食べてくれなければ意味がありません。特に療法食は味に個体差があり、猫によっては拒否する場合もあります。
メーカーによって風味や粒の形が異なるため、複数のサンプルを取り寄せて、猫の好みを探るのが現実的な方法です。無理に与えるのではなく、慣れるまでの時間も見てあげましょう。
費用や入手しやすさも考慮する
療法食は通常のフードより高価な場合が多く、長期にわたると家計への負担になることも。動物病院専売のものと通販可能なものでは価格帯や送料も異なります。
また、継続的に購入できるかどうかも重要な判断ポイント。定期便サービスやオンラインショップの活用など、自分にとって無理のない形で継続できる方法を検討しましょう。
長期使用のリスクと継続判断も想定する
療法食は病状に応じて適切な期間与えることが前提です。症状が改善されたからといって自己判断で中止したり、逆に必要のない時期に長く与えすぎたりすると、栄養バランスが崩れる可能性があります。
定期的に獣医師に相談し、体調や検査数値に応じて継続の可否を判断していくことが大切です。
もし猫が療法食を食べないときの対処法

どんなに効果的な療法食でも、猫が食べてくれなければ意味がありません。ここでは食いつきが悪いときの工夫を紹介します。
ぬるま湯で温めて香りを立てる
猫は香りで食欲を刺激される動物です。ドライフードにぬるま湯をかけて少し柔らかくすることで、香りが立ちやすくなり、食べやすさも増します。
特に腎臓病の猫など食欲が落ちやすい子には効果的な方法です。ただし熱すぎると栄養が壊れたり、猫の口を傷つける可能性があるので、人肌程度の温度を目安にしましょう。
ウェットフードやふりかけで食欲刺激
ドライタイプの療法食しか用意できない場合でも、療法食の範囲内で許可されたウェットフードや食欲増進用のふりかけを活用することで、猫の興味を引きやすくなります。
市販の猫用ふりかけをかけることで、香りや味の変化が生まれ、食べやすくなることもあります。ただし、自己判断で療法食以外のトッピングを加えることは避け、獣医師に相談した上で使用しましょう。
一時的な混合食で徐々に慣らす
急に療法食だけに切り替えると、猫が警戒して口をつけなくなることがあります。そうした場合は、以前与えていたフードに少しずつ療法食を混ぜていく「移行期間」を設けるとスムーズです。
3〜7日ほどかけて比率を変えていき、最終的に療法食のみに切り替えることで、猫の負担も減らすことができます。
猫の療法食はいつまで続ける?切り替えのタイミング

療法食は「一生続けるもの」と思われがちですが、実際には猫の体調や検査結果に応じて見直しが必要です。症状が落ち着いた場合や、成長段階の変化によっては、一般食への切り替えを検討することもあります。
ただし、その判断は必ず獣医師と相談のうえで行いましょう。自己判断で急に食事を変えると、症状が再発したり、体調を崩したりする恐れがあります。
継続すべきかどうかは、定期的な血液検査や尿検査を通じて総合的に判断するのが安心です。療法食は「治療の一環」であり、経過に応じて調整していくのが基本です。
猫の療法食の購入先と価格相場
猫の療法食は、動物病院やペットショップ、通販サイトなどで購入できます。病院専売の製品は診察とセットで案内されることが多く、信頼性は高いものの価格はやや高め。
一方、Amazonや楽天などのオンラインショップでは同じ商品でも割引価格や定期便が利用できる場合があります。ただし、通販では獣医師のアドバイスを受けにくいため、初回は必ず医師の診断を受けたうえで選ぶことが大切です。
価格は商品やメーカーによりますが、ドライタイプで1kgあたり2,000〜4,000円が目安となります。継続購入を見据えて、コストと利便性を比較検討することが必要です。
療法食を通じて猫と向き合う

療法食は単なる「特別なごはん」ではなく、病気と向き合う猫と、支える飼い主をつなぐ大切なケアのひとつです。日々の食事を通じて体調の変化に気づけたり、元気になった姿に安心したり、療法食は猫との暮らしの中で新たな絆を生み出します。
最初は戸惑いや不安もあるかもしれませんが、正しい知識と信頼できるサポートがあれば、無理なく続けていくことができます。猫の「いま」を守り、「これから」を支えるために、療法食を前向きに取り入れていきましょう。